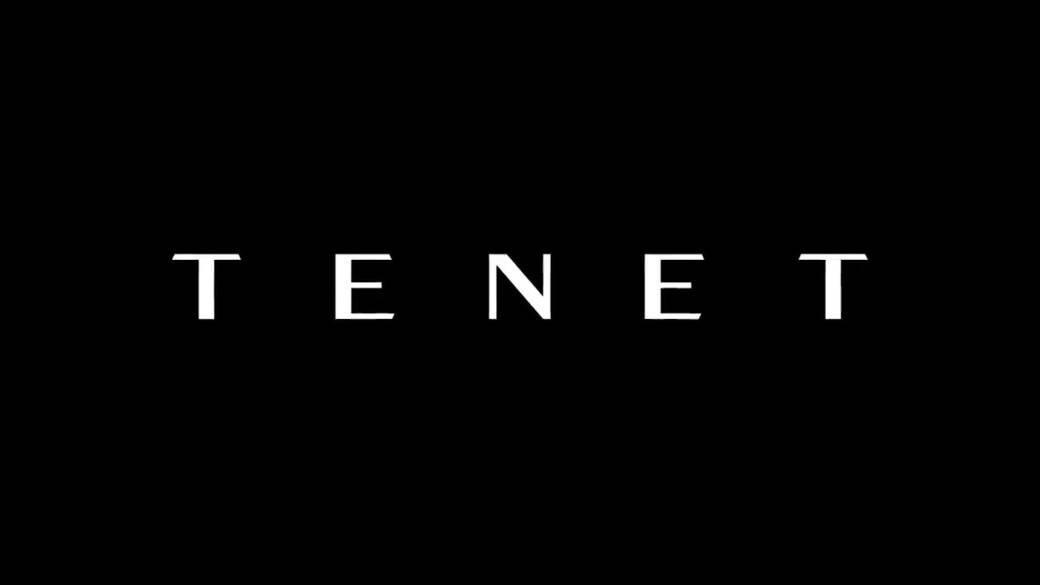カラックスと、映画を回顧『ホーリー・モーターズ』(2012)
こんにちは、星読み☆映画ライターのJunkoです!
3月に始まったレオス・カラックス監督の特集上映(於ユーロスペース)は、5月13日まで続いていたようです。
『ホーリー・モーターズ』は4月に公開された『アネット』(2021)の前作でありながら、9年もの隔たりがあり、特集上映を組んでくださって良かったなと、感謝。
今回も、事前知識はゼロで臨みました。事後に、町山智浩さんの解説(予習編・復習編)を拝見しています。
『ホーリー・モーターズ』へのひと言
カラックスの映画人生に、背伸びして付き合おう。
この作品は、主人公のいる物語として見ると、全く意味を成しません。そして分からないなりに見進めると、少なくともいくつかの別の作品を思い出したりします。
そう、これは映画のための映画であり、俳優が演じ分けていきます。
「映画鑑賞は筋トレ」とも思っているので、見続けていると、今回のような作品には役立つことがあります。
映画監督が撮る映画についての映画、ってありますよね。分かりやすく『ニュー・シネマ・パラダイス』(1989)や、オムニバス作品『それぞれのシネマ』(2007)などもそうかと思います。本作は、私的な映画史になるでしょうか。教科書ではなく、エッセイというか。
そんな訳で、『ホーリー・モーターズ』はカラックス監督が浴びるように見たであろう世界の古典から、エッジの効いた作品、ご自身の作品まで、あーでもないこーでもないと紐づけて見られる作品です。

一方で、観る側の時代も変わりました。2020年代は、映画以外のエンタメも多く、倍速で見たり、2つのメディアを並行したり、忙しくなりました。映画通同士が、「あのシーンは〜〜へのオマージュで…」と楽しむ場面も、少なくなったのではないでしょうか。共通の答え合わせはできなくても、「私はこう感じた、これを思い出した」くらいの会話が、より自然に思えます。
というわけで、この映画は気軽に観るものというよりは、カラックス監督の大ファンたちが「監督の脳内を体感して共鳴したい!」と切望して行く方が、自然に思えます。
セットにお金かかってる!
そう、カラックス監督のような鬼才の脳内を垣間見るとしたら、そこから莫大な予算がかかることは想像に難くない。『ポンヌフの恋人』で大赤字を出した監督としても知られていますが、本作でも9つのランデブー(出会い)と呼ばれる独立した場面に分かれ、作り込みを見ると相当お金がかかったのでは、と分かります。
外ではパリの街や空気感をよく捉えているし、暗い屋内や地下も雰囲気たっぷりです。
予算と興行成績はほぼトントンだったようですね。
なぜドニ・ラヴァンか
本作はレオス・カラックス監督本人も登場しますが、監督の分身と言われるドニ・ラヴァンが主人公です。ドニ・ラヴァンの何がすごいかって、身体能力の高さ。
1961年生まれのラヴァンは、13歳でパントマイム、サーカスのクラスを取り始めたようです。パントマイム師のマルセル・マルソー氏に憧れていたそうです。1982年(20〜21歳)で俳優業に入り、1984年の『ボーイ・ミーツ・ガール』でのブレイクにつながります。『汚れた血』にも、腹話術やマジックのシーンがありますね。
今回もモーションキャプチャーの出てくる場面や、ギャングと戦う場面など、ラヴァンの身体能力が光ります。しかも公開当時51歳で、あの筋肉と動きを見せられるのは立派。もちろんトム・クルーズなど「スタントなし」でシリーズものに挑む俳優さんもいますが、映画史を綴るくらいの一大プロジェクトで、さまざまなジャンルの役を演じ分けられるからこそ、起用されたのだと。心から敬服します。
タイトルがまた難しい
『ホーリー・モーターズ』(Holy Motors)と聞いて、男性が女性を抱き抱えて階段を登るビジュアルを見て、青春映画なのだと思っていました。 『アメリカン・グラフィティ』的な。
Holyは神聖な、そしてモーターズは車とか発動機とか。

鑑賞して思うのは、映画は神聖なもの、映画は「動き」(モーション)が関係していること。ポスターでは、目から映写機のような光を放っています。
そして「ホーリー・モーターズ」という会社にリムジンが駐車されています。リムジンはフランス発祥のようですが、一般的にはアメリカ臭がしますね。映画がフランス発かアメリカ発か、よく話題になりますが、産業という括りには間違いないようです。
町山さんの解説で、主人公のオスカーは、アカデミー賞の「オスカー像」から取ったという話も出ていました。ボーッとして見てしまうとそこまでキャッチできなかったのですが、うんちくを語ろうと思ったら事欠かないようです。
本作はカラックス監督作品を複数見た上で、まとめとして見るのがおすすめですね!私はこの映画から派生して、いくつか作品を見てみようと思います。