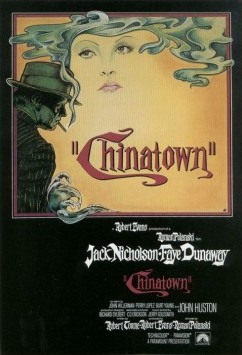時の重みを感じる、『瞳をとじて』
こんにちは、星読み☆映画ライターのJunkoです!
2月は自分の進路に影響することが起こり、近年まれに見るタイトな時間を過ごしておりました。ブログ更新がストップするほどに集中しなくてはならない状況でしたが、暖かく見守ってくださいましたら幸いです。そしてそのゾーンを抜け、映画館に行ける幸せを噛み締めました。
待ちわびていた作品は、ビクトル・エリセ監督の『瞳をとじて』(2023)。ある映画作品の撮影中に主演俳優が失踪し、行方不明のまま20数年。この俳優を取り上げたテレビ番組に、親友でもある元映画監督が出演し、当時を回顧するという内容です。
『瞳をとじて』へのひと言
時間の重さが、感じられる。
『ミツバチのささやき』(1973)や『エル・スール』(1983)が日本で公開されたのは1985年とのことですが、そこから40年が経とうとしています。その間に多くの映画監督が誕生し、多くの作品が生まれ、人々の生活も変わった。特に、デジタルへの移行で情報のスピードは格段に変わりました。手のひらサイズで動画が再生され続けたりと、映画の存在が脅かされるかのような日常。
でも、それはちがいました。登場人物は、記憶を思い起こす時にその年数分の重みがある。失踪した同僚。失踪した恋人。失踪した父。単に歳を重ねた高年の主人公、ではなく、その人が過ごして来た時間や気持ちまでが、どっと画面から伝播してきます。話すことで、当時の想いがよみがえってくるくらい、大切な思い出と喪失感。過去は軽視されていないし、偏重されてもいない。現在と同じくらいに、意味付けされています。
それをフィルムという二次元で現していることが、重鎮のなせる技。役者の演技然り、プロダクションデザインしかり。重厚感が漂います。劇中にはもちろんスマートフォンも出てきますが、人が生きるということや、人の生きた証というのは、小手先のガジェットではびくともしない重みを持っています。
映画館の立ち位置
もちろん本作は、映画という媒体についても十分に触れています。映画館でフィルムを映写したら、何か奇跡が起きるのかもしれません。ここはエリセ監督のほうが強い想いをお持ちでしょうし、映画の持つ「ワクワク感」すらもあります。
しかし監督の残酷な設定として、映画館はすでに閉館しています。人々が娯楽を求めて足を運んだのは、かつての映画館。その映画館で、フィルムが光と影を放つ時、私たちはいったい何を取り戻すのでしょうか。
良質な映画には、「層」が存在します。過去と現在に加え、虚構(映画)と現実(非映画)を行き来する登場人物たち。しかも映画制作に携わる監督や役者なわけですから、人生をかけてその道を歩んできたのです。
ワタシ的には、映画館の比喩はどうしても『ニュー・シネマ・パラダイス』(1989)の印象が強くて、少し敬遠してしまう傾向にあります。が、映画産業に生きた主人公たちであるならば、この設定もありかなと思える演出でした。