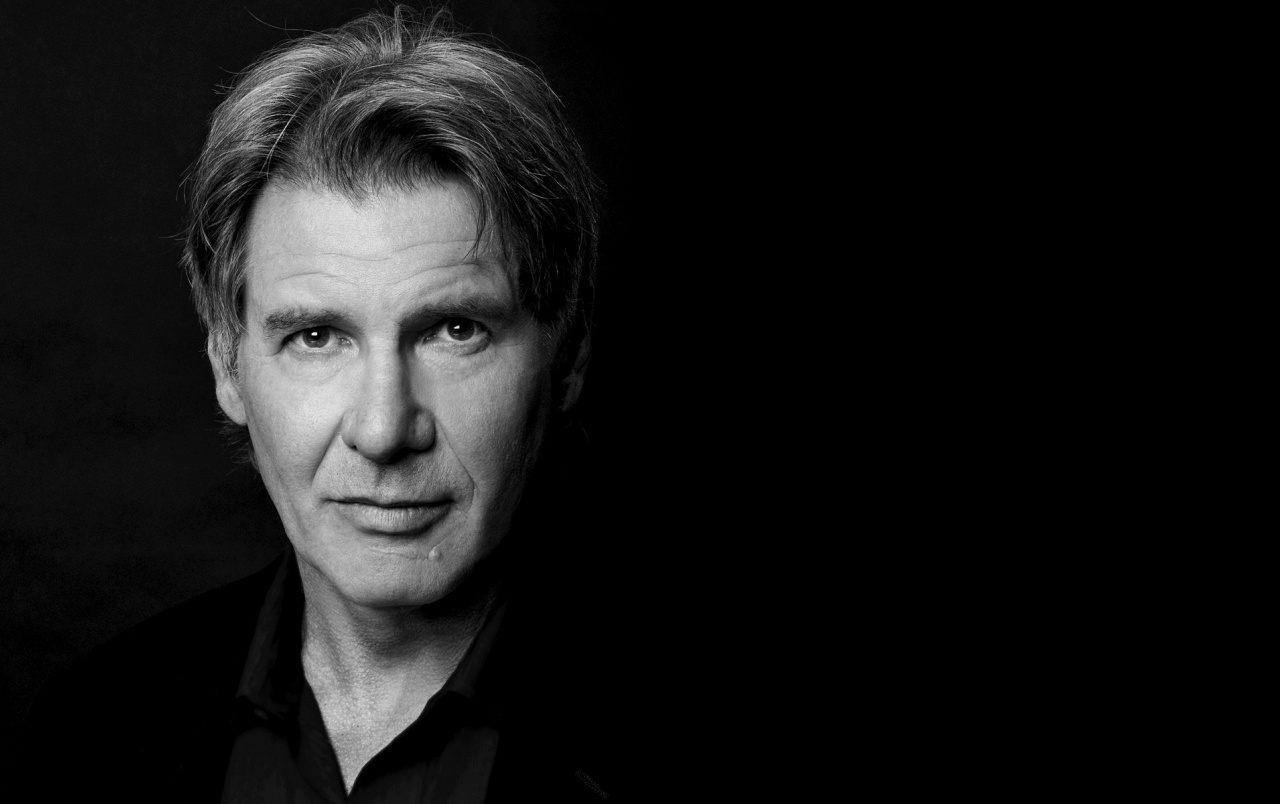『わたしは最悪。』が抵抗するものとは?
こんにちは、星読み☆映画ライターのJunkoです!
7月1日公開の『わたしは最悪。』(2021)が、各方面から絶賛のようです。ノルウェー映画ということも、興味を持ちました。
ヨアキム・トリアー監督に関しては、以前『テルマ』というホラーっぽい作品を拝見していました。が、今回の作品の仕上がりの方が、私は好きでした!
『わたしは最悪。』へのひと言
では早速、ひと言です。
恋愛や同棲は、家族になるための準備。
めちゃくちゃヨーロッパっぽいと感じたのが、そこでした。
大人の男女が(今は性別が限定されないこともある)、社会の最小単位である家族を構成すると考えるヨーロッパでは、夫婦は強い連帯関係にありますね。日本で見る「女性の集団旅行」などは、ヨーロッパでは見ません。夫婦やカップルで行くからです。
本作の主人公ユリヤも、男性とのお付き合いが始まり、同棲が始まります。そこには、関係性から「生活を共にするするのが当然」という感覚もあれば、「2人がルールに従って生活する」という2つの異なるものが1つになっていく感覚や、「共同生活をすることで、お互いを見極める」、価値観を探り合うような感覚もあります。
そしてユリヤの彼氏は10以上離れた年上で、夏に親戚で集まれば2人ともども参加し、子ども(甥っ子姪っ子)が庭で水遊びをしてはしゃいでいる。お付き合いの延長に、結婚や出産・育児が自然とあるというレールに、ある意味敷かれます。
日本だとどうだろう… お付き合いの時点で同棲しない人も多いし、家族に紹介するのはわりとお付き合いの後半かもしれません。恋愛の盛り上がりで同棲はあり得るけれども、共同生活という意識は薄いかもしれない。
『わたしは最悪。』は、ヨーロッパの家族に対する価値観を、作品全体で捉えていた気がします。この文化的差異を見るのは面白く、様々な年代の方にオススメしたいです。
30歳は大人ではない
この前提の中でギャップとして生きてくるのが、主人公ユリヤのある種幼稚なところ。大学卒業したてのような20代前半ならまだしも、30歳を迎えて自分の進みたい道が分からない。彼女は本屋で働いていますが、知的好奇心の面からも待遇面からも、魅力に感じていると思えない。この状況がリアルなんだと思います。
日本人からすると、ヨーロッパの人は同年代でも大人びて見えるし、論理的で頭よさそう!なんて思ったりしますよね。ユリヤを見ていると、その発想が少し薄れるというか、「え、このくらいブレてるんだ」と思ってしまう。
公私ともにいろいろなことを経験しながら、「ここに収まりたくない」という気持ちが、定職に就く、結婚する、という行為を遠ざける。プチブレイクはしても、大きな何かにつながることまで行かない。そういうユリヤのモラトリアム感というか、成果も出さないけど失敗もせず、焦りは蓄積する、小ぢんまりした存在に、共感が集まったのだと思います。
自然で瑞々しいヒロイン
本作の脚本はエスキル・フォクト氏(同じく映画監督)とヨアキム・トリアー監督によるもので、どちらも男性。そうすると、女心を描くのに成功したのは、主演であるレナーテ・レインスヴェさんの力が大きいと思います。
可愛らしい顔立ちで、スラッと長身ですが、やや童顔なことも相まり、彼女の行動は幼いものに映ります。大人になりたくない、なりきれない子どもを想像してしまうくらい。
映画のビジュアルにもある、走っているシーンが何なのかは言及しませんが、ユリヤの真っ直ぐで純粋なところ、その裏に高校生のように単一的で若い思考回路が、よく表れています。
ヨーロッパで童顔の女優さんは少ない印象があり(強いて言えばペネロペ・クルスですが、彼女は妖艶さが強い)、レナーテさんのように健康的に美しい大人の女性で、でも思春期の女の子のように不安定で脆さを持つ俳優をキャスティングできたことが、この映画の強みではないでしょうか!

.jpeg)