芸術家×職人の装幀者、菊地信義さんを追う『つつんで、ひらいて』
広瀬奈々子監督の新作『つつんで、ひらいて』を、東京フィルメックス2019で見ることができました。一般公開は、12月14日から(イメージフォーラム)です。

本の装幀を手がける菊地信義さんの日常を追う、ドキュメンタリーです。あの俵万智さんの『サラダ記念日』も、菊地さんご担当とのこと。戦前生まれで巨匠級の菊地さんを、 ギリ昭和生まれの新鋭監督が撮ったことが、興味深かったです。関係性は思ったよりも画に出てしまうものですが、登場人物と監督との間に、変な上下関係や居心地の悪さはありませんでした。
菊地さんに一度は断られたものの、次にお会いした時には演出目線でいろいろアイデアを出されたという、菊地さんの中での心の変化があったようです。
さて、映画では、「本が好きな人がこんなにいるんだなぁ」「本の装幀をここまで考えているんだなぁ」という驚きの連続です。なぜならカバーはそもそも本を汚れから防ぐものであり、宣伝効果がありながら多くの人にとって優先度が低いもの。これだけ大きさも材質も(そして予算も)限られた世界で、最大限のクリエイティビティを発揮するには、という挑戦があります。
この映画を一言で言うと何かな、と考えていたのですが、思い出したフレーズはこれでした。ネタばれしないようにと思いましたが、公式ウェブサイトにも紹介されていましたので。
「デザインとは設計でなく、
https://www.magichour.co.jp/tsutsunde/
誰かのために“こしらえる”ものだと思うんです」
英語字幕が出ていたんですが、こしらえるは「prepare」(準備する)を使っていました。そして続く会話では、こしらえるは他者がいること、相手のために準備をすること、それがデザインだと。おばあちゃんが孫におにぎりをこしらえる、それです。どうも設計というと、無機的というか、冷たい感じがしますものね。
もう一つ私が感じたのは、装幀の中で文字の力が大きいということです。これは言い換えれば、文化的境界線が大きいということかもしれません。日本語を解す人と解さない人では、同じデザインとは言え装幀から受ける印象も違ってきます。
菊地さんは吉本隆明さんの書籍をいくつも担当されていますが、思想を刺激するかのように文字が目に飛び込み、その印象に左右されます。もちろん文字も、ゴシックと明朝の使い分け、トレーシングペーパー(パラフィン紙)を使ってカバーの下に地のプリントが見えるなど、ガンガン攻めています。下の例で言えば、それをもう1986年にやっておられるのだから、数十歩先を走っている方だなと。

映画も本のように章立てになっており、読み進めていくような感じです。映画という媒体でもっと勝負する作りでもよかったのかもしれませんが、菊地さんをフィーチャーしている以上は、あくまでご本人や装幀がメインとなる見せ方で、穏やかに進みます。ナレーションはなく、スーパー(字幕)での説明が入ります。
監督が工夫した点としてQ&Aでお話しされていたのは「触感」で、どう取ったら 「手触り」 が伝わるかを考えながら撮影されていたそうです。

そして、本を味わうことが五感を刺激するように、映画も劇場に足を運ぶことで、五感を使って作品を味わってほしい、そんな監督の思いも受け取りました。
菊地さんに関する本もいくつか出ています。広瀬監督がご自宅ですでに目にしていたのは『装幀談義』(1986)だったとのことです。
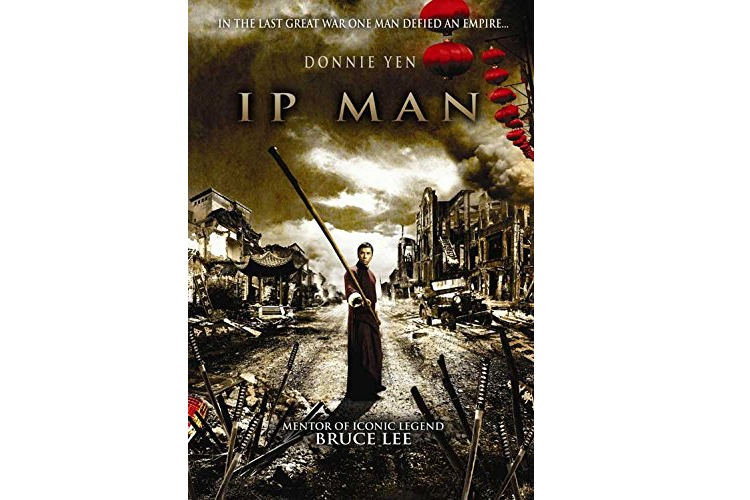
.jpeg)
